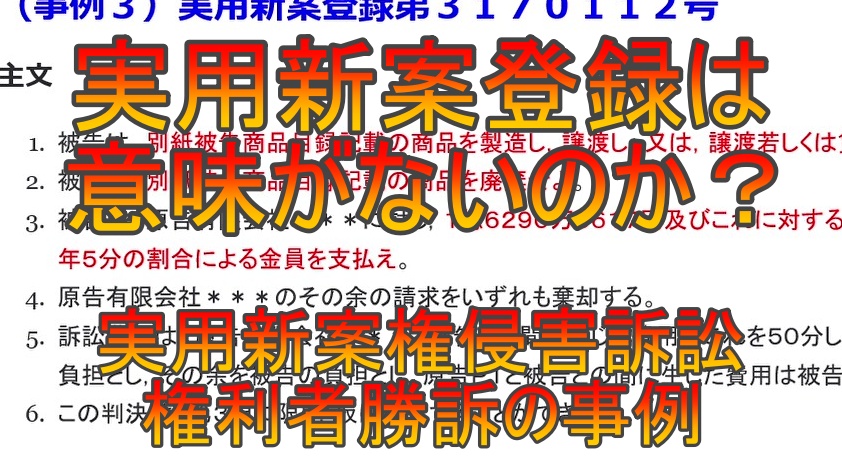
◆実用新案にはデメリットもあります。大手企業の多くが特許を選択するのは事実です。しかし、資金力に差がありますから、大手企業の知財戦略を真似る必要はありません。
◆手軽に安価にということであれば、実用新案です。
目次
- はじめに
- 実用新案登録のメリット(実用新案が意味ある理由)
- 実用新案登録のデメリット(特許と比較した欠点)
- 実用新案登録と意匠登録の比較
- 特許か実用新案かの選択
- 実用新案登録による他社牽制効果
- 中小企業による特許と実用新案の出願状況(実際の利用状況)
- 実用新案権の権利行使(権利者勝訴の事例)
>(事例1)実用新案登録第3096809号
>(事例2)実用新案登録第3157614号
>(事例3)実用新案登録第3170112号
>(事例4)実用新案登録第3159269号
>(事例5)実用新案登録第3198778号 - 本ページの解説動画1:実用新案は意味がないのか(メリット、デメリット、権利者勝訴例など)【動画】
- 本ページの解説動画2:実用新案のメリット・デメリット【動画】
はじめに
実用新案は意味がないのか、費用の無駄なのか、実用新案のメリット、デメリット、特許や意匠登録との違いについて解説します。
中小企業による特許と実用新案の出願状況についても見てみます。
最後に、実用新案権の権利行使と権利者勝訴の例についてもご紹介いたします。
実用新案でも高額の損害賠償請求や差止請求が認められることがある“事実”を知っていただきたいと思います。
実用新案登録のメリット(実用新案が意味ある理由)
(1)実用新案権も、権利の有効性があれば、特許権と同様に権利行使できます。
権利の有効性があれば(新規性や進歩性などを備えていれば)、実用新案権も特許権と同様に権利行使できます。
実際、後述の「実用新案権の権利行使」でご紹介のとおり、実用新案権に基づき、高額の損害賠償請求や差止請求が認められた事案があります。
このような“事実”がある以上、「実用新案は意味ない」ということはできません。
(2)実用新案は権利取得までの手続が楽です。
実用新案登録出願すると、「方式審査」と「基礎的要件の審査」だけで登録されます。
方式審査では、出願書類の様式がチェックされます。基礎的要件の審査では、実用新案法の保護対象か、出願書類に必要な事項が記載されているか、などがチェックされます。特許出願についてなされる新規性(新しいか)や進歩性(容易に考えられないか)などの実体的要件の審査は行われません。
そのため、本来無効となるような権利が登録されることがあるものの、手軽に、早期に、実用新案権を取得することができます。
そして、必要に応じて、「実用新案技術評価」を受けることで、権利の有効性(新規性や進歩性があるかなど)を確認することができます。実用新案登録しただけでは、有効な権利かもしれないし、そうでないかもしれない状況です。有効な権利かもしれない以上、登録が無効となるまでは、他社に対してある程度の牽制効果が働くと思われます。しかも、後述するように、一定要件下、特許への変更や、(無効を回避するための)権利範囲の減縮訂正が可能です。
従って、「実用新案は意味ない」ということはできません。
(3)実用新案は特許と比べて安価です。
特許と比べて、権利取得のための費用が、各段に安いです。
詳しくは、「特許と実用新案の費用の比較」をご覧ください。
実用新案は、資金力の乏しい中小企業や個人の方にとって、特許と比べて手軽に安価に利用できる制度となっています。
そのため、「実用新案は意味ない」ということはできません。
(4)実用新案は登録後も一定要件下、特許に変更できます。
出願日から3年以内など、所定の要件を満たせば、実用新案登録に基づく特許出願(いわば特許出願への変更)ができます。
特許出願に変更可能な状況下では、基本的には「特許出願中」と同じ効果があるはずです。
いまは実用新案でも、将来、特許になるかもしれないのです。
そのため、「実用新案は意味ない」ということはできません。
詳しくは、「実用新案登録は特許出願中と類似の状況!?」をご覧ください。
(5)実用新案でも1回は権利範囲の減縮訂正ができます。
所定要件下、実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正ができます。
このことは、現状、仮に新規性や進歩性がなさそうな内容であっても、権利範囲を減縮訂正して、有効な権利となるかもしれない、ということです。第三者を牽制するには有効と思われます。
そのため、「実用新案は意味ない」ということはできません。
実用新案登録のデメリット(特許と比較した欠点)
(1)特許と比べて存続期間が短いです。
特許権の存続期間は、原則として出願日から20年ですが、実用新案の場合、出願日から10年です。
但し、特許権を長期に維持することは非常に高額となり(特許と実用新案の費用の比較表)、途中で手放されることも多いです。
特許行政年次報告書2023年版によれば、特許権設定登録からの現存率は、5年後で84%、10年後で46%、15年後で8%となっています。
(2)権利行使に制約があります。
権利者は、実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、侵害者等に対し、その権利を行使することができません。つまり、権利行使に先立ち、評価書を提示して警告することが、権利者に義務付けられています。
そして、侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録の無効審決が確定したときは、権利者が実用新案技術評価書の評価(登録性を否定する旨の評価を除く)に基づき権利行使又は警告をしたとき、その他相当の注意をもって権利行使又は警告をしたときを除き、その権利行使又は警告により相手方に与えた損害を賠償する責めを負います。
このように、実用新案の場合、登録しただけでは、直ちに警告や権利行使ができません。警告や権利行使をするには、実質的には審査をパスする必要(肯定的な実用新案技術評価を得る必要)があります。審査をパスしなければ権利行使できない点で、特許と変わりません。
また、実用新案技術評価は、文献公知、公知文献から見た進歩性、拡大先願、先願の要件に関する評価です。そのため、警告や権利行使に際しては、その他の無効理由がないか(公知・公用技術等により無効とされないかなど)について、相当の注意を払う必要もあります。
なお、損害賠償請求には、侵害者の故意又は過失が要件となります。特許権の場合、侵害者は侵害行為について過失があったものと推定されますが、実用新案にはこの推定規定がありません。そのため、実用新案権者は、相手方の故意又は過失を立証する必要があります。
(3)権利を守りにくいです。
実用新案の場合、(無効を回避するための)権利範囲の減縮訂正の機会が限られ、権利を守りにくいです。
そのため、それを見越した出願書類が求められることになります。実際、無審査登録制度の導入時、登録前の補正の機会が限られることに関連して、特許庁は次のとおり解説しています。すなわち、「実体的な要件の審査が行われず、早期に権利付与が行われることから、出願人は自ら先行技術調査を十分に行い、質の高い明細書を作成することが求められる」とされています(特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編著『改正特許法・実用新案法解説』有斐閣,1993年)。そのため、実用新案だから出願書類が簡単という訳ではありません。
なお、念のためですが、権利範囲を相当具体化した実施例レベルの請求項でも新規性や進歩性がないのなら、特許出願しても拒絶されますし、実用新案登録しても有効性はなく権利行使できませんので、いずれで出願しても結果は同じです。
(4)その他
特許の場合、特許前の所定期間なら、国内優先権主張出願して改良発明を追加したり、出願書類に記載の範囲で権利範囲を差し替えたり、出願分割して様々な観点で権利化したりできることもあります。ところが、実用新案の場合、出願後早期に権利付与されるため、これらの手段を取りにくいです。改良発明を保護したり、他社の実施状況に合わせて権利範囲を調整したりすることが難しくなります。
但し、特許出願の場合も、出願後早期に出願審査請求して権利化してしまっては、同じことです。しかも、特許の場合、早く権利化してしまうと、早く特許料が高額になってしまいます(特許と実用新案の費用の比較表)。
なお、上記(1)~(3)のデメリットは、「実用新案登録に基づく特許出願」ができる状況なら、特許に変更することで解消できます。出願時には権利行使を重視せず、費用面から実用新案を選択した場合でも、実際に権利行使を検討する際には、特許への変更も考慮に入れます。実用新案登録後、もし出願日から3年以内に技術評価請求したい状況(たとえば侵害品を排除したい状況)になったのなら、技術評価請求するか、(特許への変更条件を満たせば)特許へ変更するか、を決めることができます。
実用新案登録と意匠登録の比較
意匠登録と比較される場合もありますが、実用新案登録とは保護対象が異なり、それぞれ役割があります。双方出願して重複保護を図ることはできます。
費用面でも、意匠登録の場合、実用新案登録と同等の効果を狙うなら(それが可能だとしても)、1件ですべて保護という訳にはいかないように思えます。たとえば、関連意匠制度を活用して、権利範囲(類似範囲)を明確にしたり、権利範囲を拡張したりするには、複数の意匠登録を行う必要があります。
特許か実用新案かの選択
上述した「実用新案登録のメリット」から明らかなとおり、「実用新案登録は意味がないことはない」です。実用新案登録も意味があります。
一方で、上述した「実用新案登録のデメリット」があり、その点には注意が必要です。
特許と実用新案登録とを比較して、もちろん特許を取得できるなら、それが一番です。
しかしながら、中小企業や個人事業主にとって、実際は費用の問題を避けて通れないと思います。
また、出願・登録すること自体で一応他社牽制になる上、実際に権利行使に至ることはまれでしょうから、手間や費用をかけて、常に登録前に審査を受けておく必要があるのか、という観点での検討があってもよいと思います。
さらに、「特許出願の必要性、特許権取得の意味」で述べたように、そもそも特許出願や実用新案登録出願をする目的は、権利を取るだけではなく、将来における自社の実施を確保する点にもあります。つまり、万一、自社が出願しない内に他社に出願されては困るので、まずは出願しておくという訳です。その後、特許出願の場合、実際に審査を受けて権利化するか否かの考慮期間(つまり出願することでもう他人に権利を取られることはないが、他人の実施を排除するには審査を受けて特許にする必要があるので、審査を受けるべきかの考慮期間)として、出願審査請求期間の3年が与えられているのです。そして、特許出願の場合、出願日から3年以内に出願審査請求しないと取下げ扱いとなり権利化できませんが、実用新案登録の場合、3年後も比較的低額で権利を維持することができます。さらに、万一の場合には、「使える権利」になるかもしれません。
「特許」か「実用新案登録」か、これに代えてまたは加えて「意匠登録」か、
保護対象、保護期間、発明等の重要度、出願の目的(自社実施を確保できればよいのか、他社実施を排除したいのか)、実施予定、権利行使のし易さ、ご予算などを考慮されて決定いただければと存じます。
次のリンク先もご参考になさってください。
- 特許と実用新案の違い
- 特許と実用新案、どちらで出願すべき?
- 特許と実用新案の費用の比較
- 特許か実用新案かの費用面からの検討
- 実用新案登録は特許出願中と類似の状況!?
- 実用新案登録後の留意点(特許に変更、技術評価、権利行使、訂正など)
- 特許出願の必要性、特許権取得の意味
- 中小企業による特許と実用新案の出願状況(実際の利用状況)
実用新案登録による他社牽制効果
実用新案権の場合、直ちに警告や権利行使ができず、また特許のように侵害者に過失が推定される訳でもありません。そのため、実用新案登録を受けただけで他社牽制効果があるのか、という疑問があるかもしれません。
実用新案登録しただけでは、有効な権利かもしれないし、そうでないかもしれない状況です。将来、審査をパスする(肯定的な実用新案技術評価が出る)かもしれないし、そうならないかもしれない状況です。
この状況は「特許出願中」つまり「特許出願したが特許になる前の状況」(特許になるかもしれないし、ならないかもしれない状況)に似ていると思います。実際、出願日から3年以内なら、特許に変更可能ですから、その場合は、まさに「特許出願中」になります。
そのため、実用新案登録済は、「特許出願中」程度の効果になると思います。詳しくは、「実用新案登録は特許出願中と類似の状況!?」をご覧ください。(なお、特許の場合、出願公開後、補償金請求権が発生しますが、その行使には、実質的には相手方への警告が要件ですし、審査をパスする(特許にする)必要もあります。実用新案の場合、実用新案技術評価を受けて、その評価書を提示して警告した後でなければ、権利を行使することができません。)
実用新案登録表示に牽制効果があるのかは議論があるかもしれませんが、権利者としては、法律上、実用新案登録表示を付するように努めなければなりません(実用新案登録表示とは)。
そのような表示をされては困る、権利が邪魔だと思う第三者は、実用新案登録無効審判を請求できます。また、権利の有効性を確認するだけなら、比較的安価に誰でも、実用新案技術評価を請求できます。
中小企業による特許と実用新案の出願状況
特許行政年次報告書2023年版によれば、次のとおりです。
特許出願について、内国人による出願の総件数は、218,813件です。その内、中小企業の出願件数は、39,648件であり、総件数に対する割合は、18.1%です。
実用新案登録出願について、内国人による出願の総件数は、2,964件です。その内、中小企業の出願件数は、1,556件であり、総件数に対する割合は、52.5%です。
実用新案権の権利行使(権利者勝訴の事例)
無審査登録制度の下で取得した実用新案権に基づき、侵害訴訟において権利行使できた事例をご紹介します。地裁判決として実用新案権に基づく差止請求や損害賠償請求が認められた事例です。少なくとも地裁において、権利者勝訴の事例となります。
件数は少ないですが、もともとの出願件数が特許と比較して非常に少ないです(2022年の出願件数)。また、権利行使に先立ち審査(実用新案技術評価)を受けますが、その結果によって権利行使を断念したケースもあると思われます。
以下、判決主文(結論)のみを示します。実用新案権に着目し、その威力のご紹介のため、事件番号は敢えて表示しておりません。判決全文をご覧になりたい場合、裁判所のホームページで検索いただくか、弊所にお問合せください。控訴審判決や関連事件を確認できたものについては、その番号もお知らせできます。
なお、実用新案権の権利行使については、「実用新案登録後の留意点」の「権利行使するには」もご覧ください。
(事例1)実用新案登録第3096809号
主文
- 被告は,原告P1に対し,別紙イ号物件目録記載の爪切りを輸入し,販売し,又は販売のために展示してはならない。
- 被告は,原告ら各自に対し,2万0897円及びこれに対する平成18年7月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 被告は,原告有限会社***に対し,11万3559円及びこれに対する平成18年7月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
- 訴訟費用は甲乙事件を通じてこれを10分し,その7を原告らの,その3を被告の負担とする。
- この判決の第1項ないし第3項は,仮に執行することができる。
(事例2)実用新案登録第3157614号(+意匠登録第1392789号)
主文
- 被告は,別紙被告製品目録記載の被告製品を製造し,譲渡し,貸し渡し,又は譲渡若しくは貸し渡しのために展示してはならない。
- 被告は,別紙被告製品目録記載の被告製品及びその半完成品(別紙被告製品目録記載の構造を具備しているが製品として完成するに至らないもの)を廃棄せよ。
- 被告は,原告に対し,20万3700円及びこれに対する平成24年4月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
- 訴訟費用はこれを10分し,その7を被告の負担とし,その3を原告の負担とする。
- この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。
(事例3)実用新案登録第3170112号
主文
- 被告は,別紙被告商品目録記載の商品を製造し,譲渡し,又は,譲渡若しくは貸渡しのために展示してはならない。
- 被告は,別紙被告商品目録記載の商品を廃棄せよ。
- 被告は,原告有限会社***に対し,1億6290万6617円及びこれに対する平成27年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 原告有限会社***のその余の請求をいずれも棄却する。
- 訴訟費用は,原告有限会社***と被告との間に生じた費用はこれを50分し,その11を原告有限会社***の負担とし,その余を被告の負担とし,原告P1と被告との間に生じた費用は被告の負担とする。
- この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
(事例4)実用新案登録第3159269号
主文
- 被告は,別紙1被告製品目録記載のプレハブ式階段を製造し,譲渡し,又は譲渡の申出をしてはならない。
- 被告は,別紙1被告製品目録記載のプレハブ式階段を廃棄せよ。
- 被告は,原告に対し,165万9952円及びこれに対する平成29年4月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
- 訴訟費用はこれを4分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
- この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
(事例5)実用新案登録第3198778号
主文
- 被告は,別紙2物件目録記載の各製品の譲渡又は譲渡の申出をしてはならない。
- 被告は,前項記載の各製品を廃棄せよ。
- 被告は,原告に対し,1537万5027円及びうち36万円に対する平成29年7月25日から,うち1306万6381円に対する平成31年3月1日から,うち194万8646円に対する令和元年5月31日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
- 訴訟費用は,これを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
- この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
(作成2021.10.16、最終更新2023.12.31)
出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。
Copyright©2021-2023 Katanobu Koyama. ALL RIGHTS RESERVED.